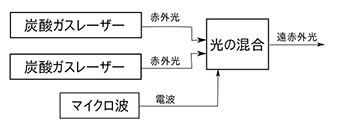研究トピックス TOPICS
- ホーム
- 研究トピックス一覧
- 物理学科の研究トピックス一覧
- 研究トピックス
宇宙最初の分子と富山大の研究
富山大学 名誉教授 松島房和
今年の4月ごろ、有名な科学雑誌Natureに「宇宙空間でHeH+(水素化ヘリウムイオン)という分子が見つかった」との報告が載り世界的に注目された。現在では宇宙空間にはたくさんの種類の分子が見つかっているが、長い宇宙の歴史でまず最初にできた分子がこのHeH+(電荷を持っているので分子イオンという)とみられている。これまで長期にわたる星間分子探査の研究にもかかわらずこの分子イオンは見つかっていなかった。やっと見つかったというのも素晴らしいが、実はこの分子を見つけるのに手がかりとなる実験データを提供したのが富山大であるということも誇らしいことである。
HeH+とは
宇宙はビッグバンによって出現し、初めに素粒子が、次に原子がそしてさらに分子ができていった。この過程では、構造が簡単な軽い原子からできていったので、初期の宇宙では大部分が水素原子(H)であと少しヘリウム原子(He)が存在するくらいで、その他の原子はごく微量だったはずだ。分子ができたとすると 1番目と2番目に存在量の多い水素原子とヘリウム原子がくっついてできるだろうと想像するのは当然で、候補として考えられたのは水素とヘリウムの原子がくっついて電子を1つ放出しプラスの電荷を持ってできるHeH+という分子イオンだ。この分子イオンは別の見方をすると、ヘリウムの原子に水素の原子核(陽子)がついたものともいえる。この分子イオンが宇宙の初期からできて今も宇宙のあちこちにあってすぐ見つかりそうだと思われた。ところが星間分子を探査している研究者が長いこと探していたにもかかわらずこの分子イオンは見つかっていなかった。なぜだろう。
星間分子の見つけ方
分子は振動したり回転したりして電磁波を放出する。電磁波は電場や磁場の振動する波で光の速度で伝わる。波が1秒間に振動する回数は周波数と呼ばれ、また、波1つの長さは波長と呼ばれる。電磁波の違いは周波数(単位はヘルツ)で言ったり、波長で言ったりするが、どちらで言っても同じだ。我々の目に見える可視光でいえば色の違いで区別していることに相当する。
分子が振動するとおよそ赤外の領域の光が出る。分子の回転からはもっと周波数の低い光すなわち電波と言われる領域の電磁波が出る。1種類の分子はいろいろな振動や回転のおかげでたくさんの周波数(すなわち色)の電波や光を出すことができるが、ここで大事な事は、出す周波数の組み合わせ(スペクトルという)は分子ごとに決まっているということだ。分子が異なると周波数の組み合わも異なる。人間の指紋と同じだ。そこで分子が出す光の周波数のリスト(スペクトル)を実験室で測っておき、宇宙から来る光を受けて調べればお目当ての分子がいるかどうかがわかる。HeH+という分子イオンも宇宙で回転による電磁波を出しているはずなので、その出している周波数の電磁波を受信して確認すればよいのだが、ここで2つの問題があった。1つ目。HeH+は軽い分子イオンであるため、出す電磁波の周波数が高くて、電波といっても光に近い領域(遠赤外領域)の電磁波を出す。そしてこの遠赤外の領域のスペクトルを実験室で正確に測るのはとても難しいのだ。2つ目。宇宙から来る遠赤外の光は大気中の水蒸気に吸われてしまって地上ではなかなか観測できないということだ。これら2つの問題がどう克服されたかを以下に紹介する。
富山大の高精度な遠赤外スペクトル測定
実験室で分子のスペクトルの正確な周波数を計るためには、そのスペクトルと同じ周波数の光を人工的に発生させて分子がその光を吸収するかどうかを確認すればよい。遠赤外より高い周波数の光の領域ではさまざまなレーザーが開発されてきてこの役に立ってきた。一方、遠赤外より低い周波数の電波の領域ではいろいろなエレクトロニクス技術の電波発振器が開発されてきた。電子レンジなどはその応用である。ところがHeH+の回転スペクトルは遠赤外の2x1012ヘルツ(波長で言えば0.15mm)ぐらいのところにある。ちなみに、1012とは数字のあとに0が12個つくという意味で、100万の100万倍という大きな数字だ。この遠赤外は、レーザーには低すぎる、電波発振器には高すぎるという周波数領域で、世界中の研究者が工夫を重ねながらもなかなか欲しい光が出せなかった。
そこで富山大学では赤外のレーザーとしてよく使われている炭酸ガスレーザーを2本用意し、少し違った周波数の2本の赤外レーザー光を作り、それら2本の赤外光の差の周波数の光として遠赤外光を発生させるという方法をとった。つまり光を合成して新たな光をつくるという方法だ(図1を参照)。実際の実験装置では、周波数を調整するために、この合成した遠赤外光にさらにもう1つ電波も合成するという難しいことをやっている。これで弱いながらも遠赤外の光を作ることができ、測定が可能になった。調べる対象のHeH+イオンはHeガスと水素ガスをガラス管の中に入れて放電させて作る。その放電管の中を遠赤外光をとおしてどんな周波数のときに光がHeH+に吸収されたかを調べればよい。図2はその実験結果で、光の周波数を変えながらスペクトル線の微分形を描いたものだ。もともとスペクトル線は線とは言っても幅を持つので1つの山のような形をしている。その山の形そのものではなく山の斜面の勾配(傾き)を記録したものが微分形だ。なんでそんなややこしいもので記録するのかというと、そのほうが測定がしやすいからなので仕方ない。われわれが知りたいのはスペクトル線の中心をあたえる周波数だ。山で言えば頂上をあたえる周波数であり、微分形の場合は水平の位置を横切る場所の周波数だ。測定結果は2.0101838x1012ヘルツだった。1996年のことである。
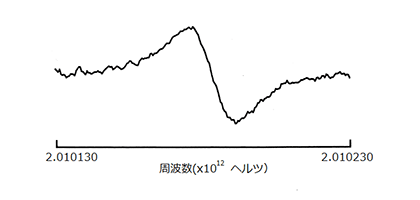
線の中心部分の周波数を精度よく測った。
この線が宇宙でも検出された。
宇宙のHeH+の探査
宇宙から来る遠赤外の光を受けるには、大気の水蒸気による吸収を避けなければならない。
そのために研究者はいろいろな手立てを考えてきた。空気の薄い高い山に受信機を置く方法(南米チリの高山で行われているALMAプロジェクト)、人工衛星に受信機を積んで宇宙空間に送り出す方法(Herschel衛星)、飛行機に受信機を載せて高空で観測する方法(SOFIAプロジェクト)などだ。富山大の測定から20年以上たった今回のHeH+発見は3番目のSOFIAの観測結果によっている。実は富山大の測定のあと、数年後に一度それらしい報告があったのだが、あいにく装置の分解能(人間でいえば目の良さ)が足りず、HeH+のスペクトル線の近くにあるCHという分子(炭素と水素でできた分子)のスペクトル線と区別がつけられなかったのだ。それでHeH+発見とは言い切れなかったわけだ。しかし、20年のあいだ人間は絶えず努力してさまざまな改良をしてきた。SOFIAに乗せる受信機の分解能はどんどんよくなって、隣のCHのスペクトル線とHeH+が区別できるようになり今回の成果になったのだ。
20年の間には実験室の測定も進歩した。遠赤外の光はまだまだ作るのは難しいが、その代わり赤外スペクトルの測定精度が飛躍的に向上した。2年ほど前にアメリカのグループがHeH+の振動のスペクトル(赤外)を精度よく測定し、それを元に直接でなく間接的にHeH+の回転スペクトルを計算し、富山大の測定を確認している。間接的な手法は刑事ドラマで言えば「犯行を見た人はいないが周囲の状況からお前が犯人としか考えられない」といって追い詰めるやり方だ。これに対し富山大の仕事は「私、この人が実際に手を下すところを見てたんです」ということだ。
富山大の独創性
ここで紹介したような遠赤外の精密測定ができるのは実は現在でも世界中で富山大だけといってよいだろう。測定実験には、装置に必要な炭酸ガスレーザーを自作して市販品では買えないほどの高精度な周波数のレーザーを作り上げることや、やっかいな赤外レーザーの周波数をしっかり制御する技術をもつことなどが必要であり、世界に大学や研究所などがたくさんあっても、それらはおいそれと簡単にはできないということがある。また、もし企業がこのような測定装置を手がけようとするなら豊富な資金と人材でよいものができるだろうとは思うが、きっと収益になるかどうかの判断から企業は手を出さないだろう。「知の地平を広げる」という純粋な科学研究の活動を大切にする大学ならではの研究であり、富山大学の独創的な成果といえる。