研究トピックス TOPICS
- ホーム
- 研究トピックス一覧
- 物理学科の研究トピックス一覧
- 研究トピックス
量子臨界〜四極子近藤効果と熱電能のおはなし
【物理学科】桑井 智彦
今からちょうど7年前に「熱電能で電子の量子状態を探る」のタイトルで「f電子系化合物」の熱電能が絶対零度付近の極低温領域で示す量子的な異常についてをこのトピックス内でご紹介しました。それから7年が経ち,この類の話題は今どうなっているのかを今回ご紹介しようと思います。
熱電能(S )は,概して棒状に整形された金属や半導体物質の片端をヒーターなどで加熱して両端間に温度差ΔT を作ると,それによって起電力(電圧)ΔV が誘起される現象を特徴つける物理量であり,S = ΔV /ΔT で表されます。単位は[ V/K ](V:ボルト,K:絶対温度)です。これを少し変形してΔV = SΔT とすると,S はΔT を入力としてΔV が出力となる関係の比例定数となることがわかります。温度差により生じる起電力であることから「熱起電力」と呼ばれ,その比例定数が大きいほど大きな熱起電力が生じることから「熱電能」と呼ばれます。温度差ΔT が消失すればΔV はゼロとなりますが,逆にΔT が生じている限りΔV は維持されます。従って温度差が連続的に生じている状況を作れば,連続的に起電力が生じ,S の絶対値が大きければ大きいほど,同じ温度差でも大きな熱起電力が得られます。棒状の物体であれば小さな熱投入でも温度差が付きやすい利点があえるので,実験ではそのような形状を用いますが,任意の形状でも温度差さえあれば熱起電力が生じることに変わりはありません。この性質を利用して,S の絶対値の大きな物質を温度差のある環境におけば,大きな起電力が得られるため,廃熱利用のクリーンエネルギーを引き出せることが期待されます。実際に,バイクのマフラー部分などにこの「熱電材料」を組み合わせて電力を取り出すなどの試みがなされたりしているのをはじめ,その分野での応用のための研究開発が進んでいます。
ところで,温度差が生じるとなぜ起電力が生まれるのでしょうか。それは物質中の電子が電気と熱エネルギーを同時に運ぶ担い手であることに由来します。電子は絶対温度Tに比例した熱エネルギーを受け取り,それを運動エネルギーに換えて物質内を「伝導電子」として移動しています。そこにさらに加熱により作られた高温端と低温端付近の電子の間に熱エネルギー差が生じるため,高温端付近の電子と低温端付近の電子の移動速度に差が生じます。これが原因となり時間平均として定常的に高温端付近の電子数は低温端付近の電子数を下回ることになります。つまり,低温端に電子が相対的に余分に存在することになります。伝導電子は移動により運動エネルギーの形で熱エネルギーを運ぶと同時に1個あたり1.6×10 -19 クーロンの電荷を伴っていますので,物質内にアボガドロ数程度の莫大な数存在している電子の数の偏りが生じ,電荷の偏り,すなわち電場が発生します。この電場が起電力の原因となります。実際には,電子は物質内の様々な要因によってその移動を妨げられたり,加熱で生じる以外の熱エネルギーを受け取り,より大きな移動速度を得たりする場合があり,S の値は物質により大きく変わり,正負の符号を持ち,1 μV/K(μ:マイクロ・百万分の一)に満たない小さな値から,数10 mV/K(m:ミリ・千分の一)に至る大きな値を示します。
原子番号58のセリウム(Ce)から70のイッテルビウム(Yb)は希土類元素と呼ばれる元素群ですが,これらの元素を含む化合物は磁気的性質をよく示すことが知られています。これらの元素に特徴的なことは,磁性,すなわち,さまざまな磁気的性質を担う「4f電子」を持つことです。たとえば,4f電子を3個持つネオジム(Nd)元素は,鉄(Fe)やホウ素(B)とで作る化合物,いわゆるネオジム磁石として知られる超強力な磁力を生じさせる要因となっています。
7年前のトピックスにも記述しましたが,今から40年近く前の1970年代の後半にCeAl3というCeとアルミニウム(Al)の化合物が絶対温度1 K以下の低温で物質内電子の質量が自由電子の質量(9.1×10-31 kg)に近い銅(Cu)などの通常金属のものに比べて1,000倍以上も大きな異常な「重い電子」状態になることが発見されました。重い電子が現れる原因は,各Ceイオン上の4f電子が周りを囲む伝導電子との間で「近藤効果」を起こすことにより,磁気的性質をもたらす4f電子「磁気モーメント」が伝導電子の持つ電子磁気モーメントにより温度低下とともに強く「遮蔽」されていくことにあります。ここで磁気モーメントとは,4f電子や伝導電子が持つ磁気的性質の原因となるもので,極微の磁石のようなものをイメージするとわかりやすいと思います。さらに「遮蔽」とは,例えばN極が上を向いた4f電子極微磁石とN極が下を向いた伝導電子極微磁石がペアを作っており,これを離れた位置からみると両者の磁力が打ち消し合って磁石が実質上,消失したように見える状態をいいます。この遮蔽効果によって,すべてのCeイオン上の4f電子磁気モーメント間に通常は現れる「磁気相転移」などの整列現象が絶対零度付近にまで抑えられてしまい,その代りに重い電子状態が現れる,というものです。この効果の名称は,この異常現象が近藤淳博士よって解明されたことに由来します。これら初期の発見に刺激を受けて,世界中の低温物性研究者が同様な異常を示す新物質の発見に尽力し,発見された多くの物質群は今では「重い電子系」と呼ばれ,固体物理の重要な研究テーマの一つになっています。また,最近では,数多くの類似物質に加え,物質内のf電子同士に強い相互作用を持ちながら磁気転移温度が絶対零度まで抑えられた「量子臨界〜量子相転移」を示すf電子化合物が見出されるようになりました。さらにこの量子臨界の近傍では従来型のBCS超伝導とは異なる「磁気揺らぎ」を媒介とした,非従来型の超伝導が発見されてきました。そのメカニズムは酸化物高温超伝導体と共通性があることが指摘され,現在もこの分野の研究者間に大きく注目されています。量子臨界近傍のふるまいは,上に述べた通常の重い電子状態と似て非なるもので,特徴的な電子質量の増大が,概ね10 K以下の極低温における比熱C に顕著に観測されます。C を絶対温度T で割ったC/T は,その物質の持つ電子の質量にダイレクトに比例します。通常の重い電子状態では,温度の低下に伴い,電子質量の増大を意味するC/T の対数的増加を示した後,絶対零度極限で大きな一定値を示します。量子臨界近傍の物質でも同様な対数的増大が観測されますが,それが絶対零度極限まで継続するのが特徴で,このふるまいはその傾向が維持されれば,絶対零度でC/T が対数発散することを意味しています。熱電能Sを絶対温度Tで割ったS/T は熱エネルギーを運ぶことに由来して,C/T と相関が強く,電子の質量が重たくなるふるまいがC/T に観測されたときは,熱電能S/T にも同様な対数的増大が観測されることが,私たちのグループを含むいくつかの研究グループにより明らかにされてきています。一例としてCe〜Cu〜金(Au)の化合物で量子臨界物質として知られるCeCu5.9Au0.1のC/T とS/T のふるまいを図1に示します。[文献1] 温度軸を対数表示にしているので,C/T とS/T はともに直線的に見えますが,4 K以下0.3 Kまでの測定で両者が連動して対数的に増大していることが分かります。この結果から,最低温度でこの物質の電子が自由電子の実に2,500倍近くも質量の重い電子状態になっていることがわかります。
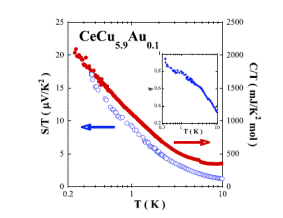
赤色がC/T,青色がS/T を示す。
上で述べたのは,磁気相転移をもたらす磁気的相互作用と逆に磁気相転移を抑える近藤効果の競合として現れると理解されている「磁気的」量子臨界異常ですが,他にも異なるタイプの量子臨界異常に関連した現象がごく最近に見出されています。3年ほど前に東大物性研グループが希土類元素プラセオジム(Pr)とバナジウム(V)およびAlの化合物PrV2Al20 という物質が低温で「四極子近藤効果」を示すことを見出したと発表しました。[文献2] 「四極子」とはおおざっぱにいうと電子の軌道上の電荷分布を指します。原子核にクーロン力によって捕えられ,原子単体を構成する電子の軌道は球状の形状(球対称)をしています。化合物結晶を構成する要素として原子が物質内に入ると,その原子上の電子軌道は周囲の電荷分布の影響を受けて結晶の対称性を反映した球対称からのずれが生じます。球対称からのズレを表したものの一つが四極子(電気四重極モーメント)です。四極子はPrイオン上の4f電子が持つ場合があり,Prイオン上のこれらの四極子,すなわち電子軌道―電荷分布はある低温において整列することが実験で明らかにされており,これを四極子転移と呼びます。PrV2Al20 では四極子転移が0.6 Kという絶対零度に迫る極低温において観測されています。このような絶対零度近くで四極子転移が生じるということは,四極子転移の原因である四極子同士にはたらく四極子相互作用と,軌道整列をさせないようにはたらく4f電子の四極子と伝導電子間の「四極子近藤効果」が競合・拮抗しているという解釈を導きます。この競合状態は上に書きましたような磁気相転移〜(磁気的)近藤効果の関係に類似しています。その意味で四極子近藤効果は,4f電子の四極子を伝導電子が遮蔽する効果であると考えることができます。そして,(磁気的)近藤効果と同様に四極子近藤効果の特徴として,ある低温以下で伝導電子の質量が増大することが理論的に予言されており,それがC/T に実際に観測された,というのが四極子近藤効果の証拠であると主張されました。実は,この理論は今から30年近く前の1987年に米国の物理学者によって提案され,当時より研究者は,こぞってこの異常を示す物質の発見に力を注いできました。これまでにいくつかの候補となる物質が発見され,低温において巨大なC/T が確かに観測されました。しかし,四極子は結晶のひずみに対してある種の弱さを持ち,結晶の乱れによってその存在が消滅するという厄介な性質を持ちます。さらに厄介なことに,もしそれが起こっても,C/T は大きな状態を観測してしまいます。すなわちC/T が巨大になっても,必ずしも電子質量が大きくなっているとは限らないということです。
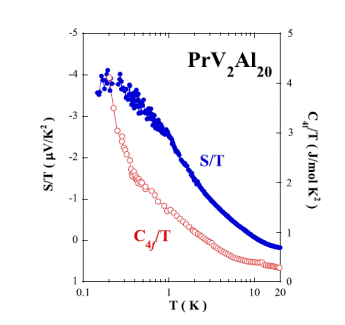
S/T の軸(左側)は比熱との比較をしやすくするために符号反転してある。
20 K以下から両者が連動して大きくなっていることがわかる。
0.3 Kにおける電子質量は自由電子の2,000倍程度。
そこで熱電能の出番となります。真に電子の質量が大きくなってC/T が巨大になるなら,熱電能も連動して巨大なS/T を持つことが期待できます。そう考えて私たちの研究グループでは,これまでに四極子近藤効果を示す系としての候補物質の熱電能を0.15 Kまでの極低温まで測定しましたが,残念ながら結果は否定的で,大きなS/T は観測されず,ほぼゼロの小さな値しか観測されませんでした。[文献3] このことはC/T の増大は結晶の乱れが原因で,電子質量が大きくなっているわけではないことを意味しており,これまでのところ四極子近藤効果が確定できた物質はありませんでした。そのような中でPrV2Al20が新しく候補物質として登場してきたわけですが,発表を受けてさっそくこの物質の熱電能を測定したところ,図2に示すように, C/T と連動した,対数的に増大する絶対値の大きなS/T が見事に観測されました。[文献4] この観測結果によって,理論的予言から30年近くを経て,ようやく四極子近藤効果を示す物質の存在が確定できました。四極子近藤効果と四極子相互作用の競合の結果生ずると期待される四極子量子臨界異常を見つけるために,現在では,国内外で日夜精力的に同種の研究が続けられています。
長々とおはなしして来ましたが,上に述べたf電子系化合物の熱電能については測定を行っているグループは数が少ないのですが,だからこそ,時として物性異常を探るための非常に強力なツールとなります。外から見ている限りは,特に異常もない単なる物質(塊)ではありますが,その内部では秩序だった整列が起きたり,逆に整列が抑えられて異なる状態が現れたり,さらには大きな発見となった超伝導など,私たちの日常とはかけ離れた量子力学に支配される魅力的な世界に満ち溢れています。自分の作製した新物質が新たな魅力的な物理特性を示すかどうかを自らの手で物性実験により探ることは,学部や大学院の学生にとっても非常に刺激的な学術研究の場となっています。
【文献】
- T. Kuwai et al. : J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) SA 064.
- A. Sakai and S. Nakatsuji: J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) 063701.
- Y. Isikawa et al.: J. Magn. Magn. Mater. 310 (2007) 289.
- T. Kuwai et al.: J. Phys. Soc. Jpn 82 (2013) 074705.
