教員と研究テーマ
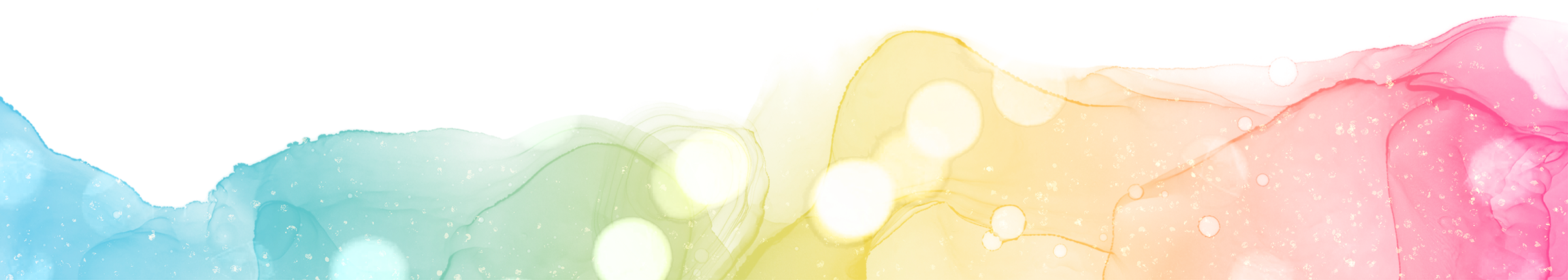
青木 一真 教授
大気物理学、地球環境科学
青木研究室(大気物理学・地球環境科学)では、雲と大気中に浮遊する微粒子(エアロゾル)の気候影響について、極域から熱帯、海洋から山岳に至る世界中で太陽放射観測などを行い、地球温暖化や気候変動など大気環境の諸問題の解明に取り組んでいます。さらに、大気物理学を視点に、海洋・雪氷・山岳・森林生態などの地球環境の融合研究、微粒子による健康影響や再生可能エネルギーなどの分野横断研究も取り組んでいます。中部山岳国立公園内・立山連峰の標高2839mにある富山大学立山施設(立山・浄土山南峰山頂)の管理人のひとり。

-

スカイラジオメーターによる地上観測
(魚津埋没林博物館) -

スカイラジオメーターによる海洋観測
(海洋地球研究船「みらい」JAMSTEC) -

積雪深6mにもおよぶ立山積雪調査
(立山・室堂平:標高2450m)

エアロゾルと雲の気候影響に関する研究
雲や大気中に浮遊する微粒子(エアロゾル)が地球の気候に与える影響について、極域から熱帯、海洋から山岳域まで、世界中で太陽放射観測などを行い、地球温暖化などの気候問題の解明に取り組んでいます。
国内外のさまざまな研究機関(JAXA,NASA,ESA,JAMSTEC等)や大学(北大,九大,長崎大,リール大,UCSD/SIO等)と研究をしています。

山岳大気の研究
立山積雪調査は、1970年代から始まり、毎年、立山・黒部アルペンルートが全線開通する4月中旬に、富山大学理学部が中心(立山積雪研究会)に様々な教育・研究機関が集まり、半年間、立山に降り積もった約6mの雪の調査を行っています。



